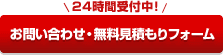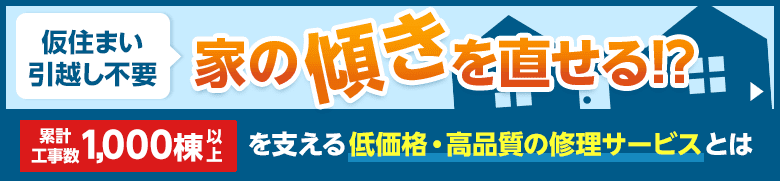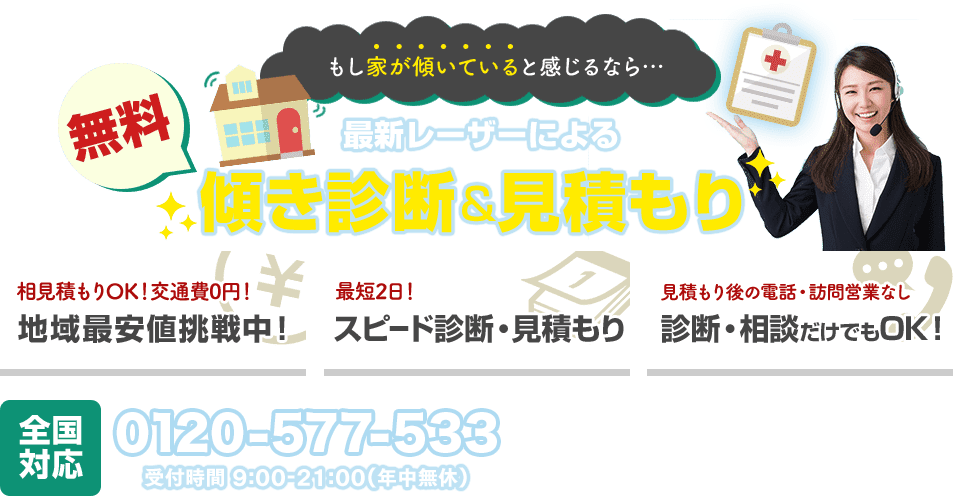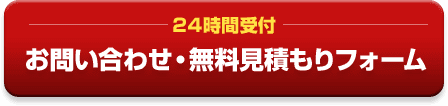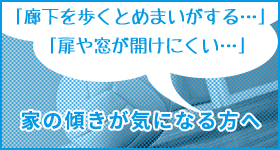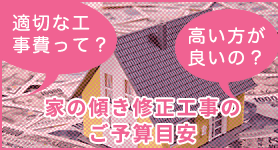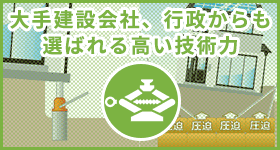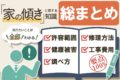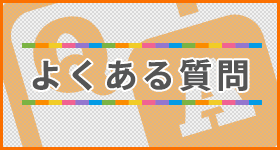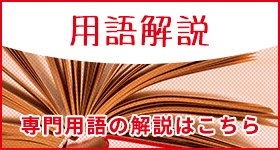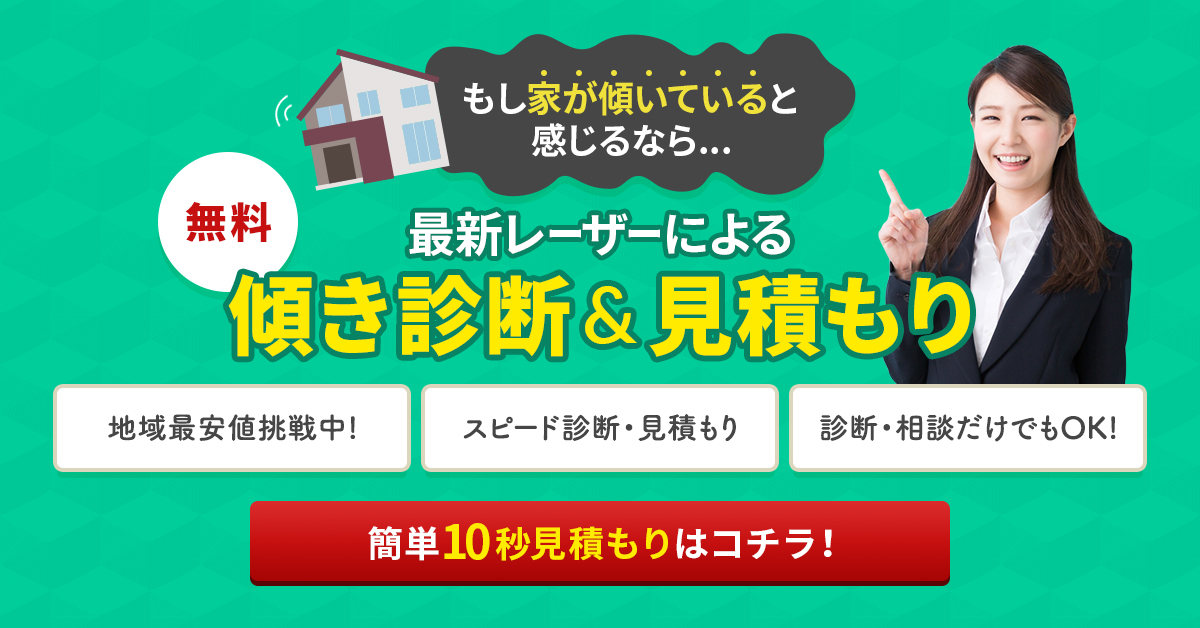基本設計図とは
基本設計図は、建物を建てる前に作る設計図の一つです。建物の大きな形や間取り、外観などの基本的な内容を示した図面のことを指します。建物を建てたい人(施主)と設計者が、建物の全体像を確認し合うために使われます。
この図面は、建築確認申請や工事の見積りを行う際の基準となります。また、このあとに作られる詳しい図面(実施設計図)の土台となる重要な図面です。
基本設計図の種類
| 図面の種類 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 配置図 | 敷地内での建物の位置を示す | 日当たりや周辺との関係を確認 |
| 平面図 | 各階の間取りを示す | 部屋の配置や動線を確認 |
| 立面図 | 建物の外観を示す | デザインや高さを確認 |
| 断面図 | 建物を切った時の様子を示す | 天井の高さや階段の勾配を確認 |
基本設計図の内容
基本設計図には、建物の重要な情報が記載されます。例えば、建物の大きさ、部屋の広さ、窓や扉の位置、屋根の形などです。図面には物差しとなる縮尺が示されており、実際の大きさを理解することができます。
一般的な住宅の場合、配置図は500分の1や200分の1、平面図は100分の1や50分の1の縮尺で描かれます。これは実際の長さの500分の1や100分の1の大きさで図面が描かれているという意味です。
基本設計図の作成過程
基本設計図は以下の手順で作成されます:
- まず施主の要望を聞き取り、必要な部屋の数や広さ、建物の雰囲気などを整理します。次に敷地の形や大きさ、建築可能な範囲を確認します。その後、法律で定められた建ぺい率や容積率、高さ制限などの規制を確認。これらの条件をもとに、建物の配置や形を検討し、徐々に図面を作り上げていきます。作成の過程では、日当たりや風通し、周辺の建物との関係なども考慮に入れます。
基本設計図の確認ポイント
基本設計図を確認する際は、まず法律に定められた規制を満たしているかを確認します。建ぺい率(敷地に対する建物の占める割合)や容積率(敷地に対する建物の床面積の割合)が制限内に収まっているか、道路からの後退距離は十分かなどを確認します。
次に、生活のしやすさという観点から確認します。部屋の広さは十分か、移動がしやすい間取りになっているか、収納は適切に配置されているか、などを細かくチェックします。また、予算との整合性も重要な確認項目です。
実施設計との関係
基本設計図が確定すると、より詳しい図面である実施設計図の作成に移ります。実施設計図では、基本設計図に加えて、細かい寸法や使用する材料、設備の配置などが具体的に示されます。
基本設計図から実施設計図に進む過程で、構造上の理由や、設備を収める空間の確保のために、間取りや外観に変更が必要になることがあります。そのため、基本設計の段階から、ある程度の余裕を持った計画としておくことが大切です。
実施設計では電気や給排水などの設備図も作成されます。これらの設備を収めるスペースを、基本設計の段階から想定しておく必要があります。例えば、配管を通すための天井の高さや、空調の室外機を置くスペースなどです。