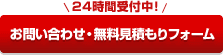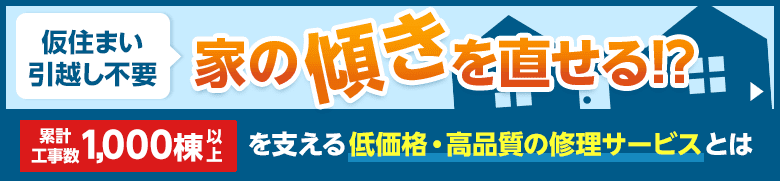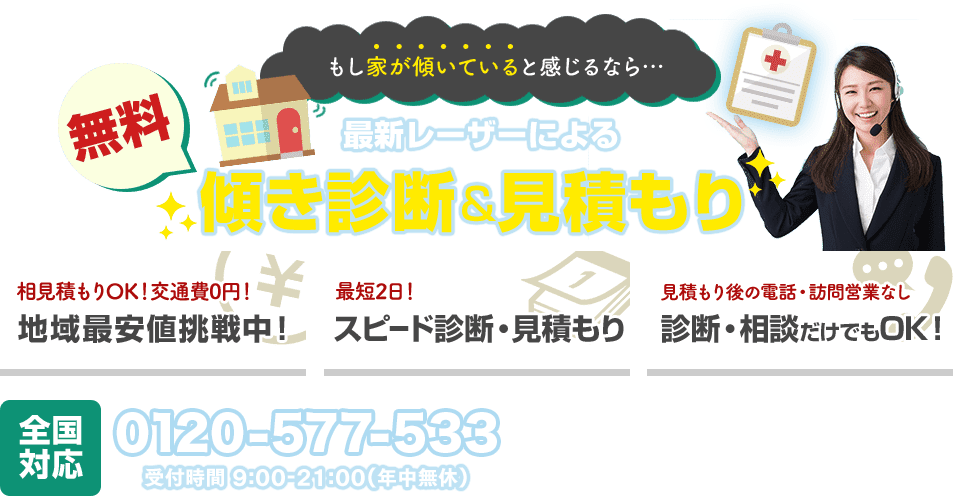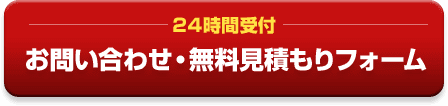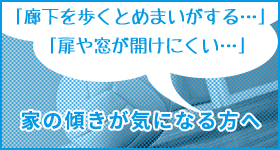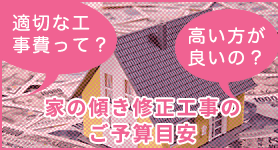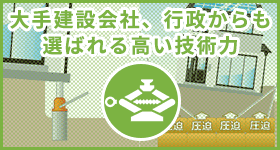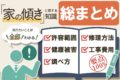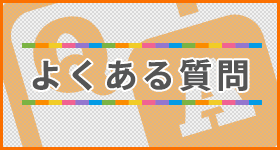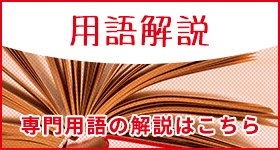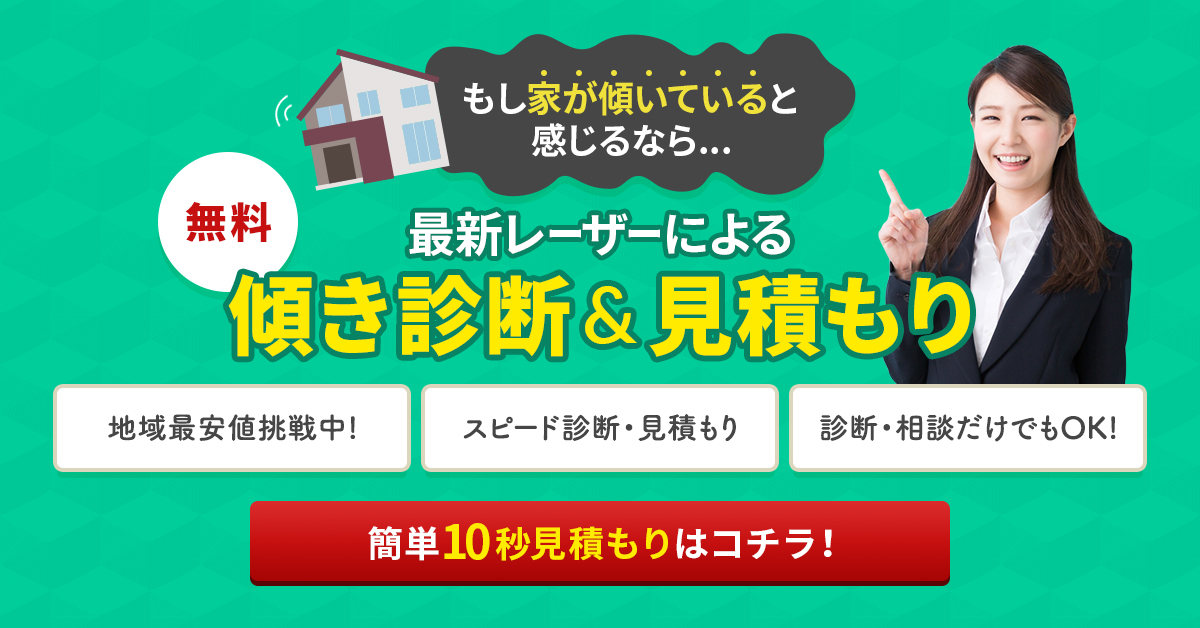棟木(むなぎ)とは
棟木(むなぎ)は、家の屋根の一番高い部分にある横木のことです。屋根の頂点に取り付けられ、屋根全体を支える大切な役割を持っています。棟木があることで、屋根の形が保たれ、家全体が丈夫になります。
棟木の基本情報
棟木は、屋根の頂上部分(棟:むね)に水平に渡される木材です。左右から傾斜して集まってくる屋根の部材を受け止め、建物全体の強度を高めています。昔から日本の家づくりでは、棟木は家の背骨とも言われるほど重要な部材として扱われてきました。
棟木の構造的特徴
棟木は通常、丸太や四角く加工された木材を使います。大きさは家の規模によって異なりますが、一般的な住宅では15cm×15cm程度の太さのものが使われることが多いです。木の種類は、杉や松などが伝統的に使われてきましたが、最近では強度を高めた集成材なども使われています。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 形状 | 長方形または丸太形 |
| 材質 | 杉、松、ヒノキなどの木材や集成材 |
| 一般的なサイズ | 15cm×15cm程度(住宅規模による) |
| 長さ | 建物の棟の長さに合わせる |
棟木の設置方法
棟木は、まず屋根の両側から伸びる垂木(たるき)と呼ばれる斜めの木材を支えるように置かれます。棟木を支えるために、柱の上から伸びる束(つか)という縦の木材が使われることもあります。これらの部材はすべて、金具や伝統的な継手・仕口(つぎて・しぐち)という木組みの技術で固定されます。
棟木を設置する際の大切なポイントは、まっすぐに水平を保つことです。棟木がゆがんでいると、屋根全体の形が崩れてしまい、雨漏りなどの原因になってしまいます。
棟木の種類と選び方
棟木には主に以下のような種類があります:
- 和風建築の棟木:伝統的な日本家屋では、見た目も美しい良質な木材が使われ、継手技術を活かした複雑な組み方がされています。
- 洋風建築の棟木:洋風の建物では「リッジビーム」とも呼ばれ、金具を多用した固定方法が特徴です。
棟木のメンテナンス
棟木は家の中心部分にあり、雨風にさらされるため、定期的な点検が必要です。特に古い家では、棟木の腐りや虫食いがないか確認することが大切です。屋根裏に入れる場合は、天井や小屋裏から棟木の状態を確認しましょう。
棟木に問題が見つかった場合は、建物の安全性に関わるため、すぐに専門家に相談することをお勧めします。棟木の交換は大がかりな工事になることが多いですが、家の寿命を延ばすためには必要な場合があります。