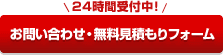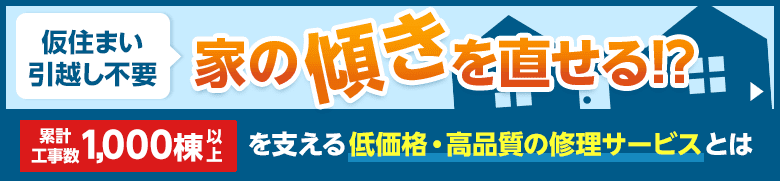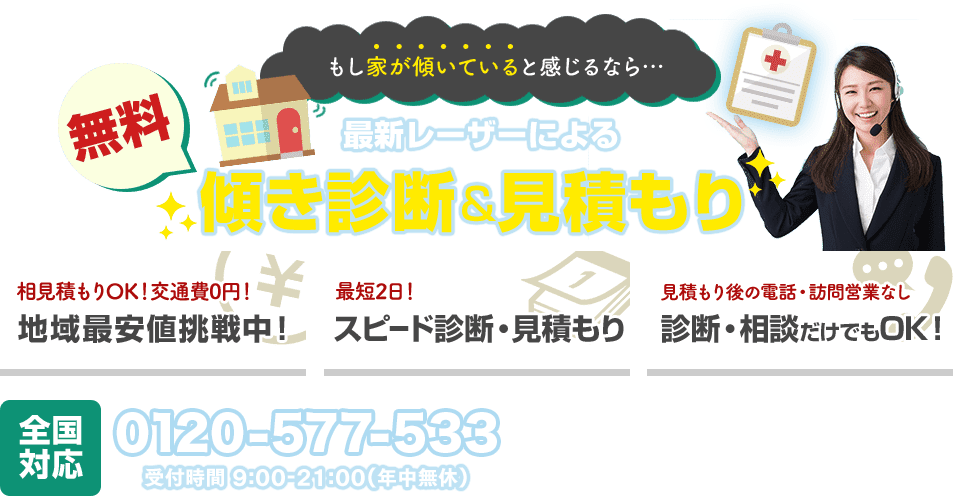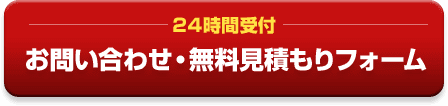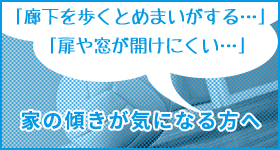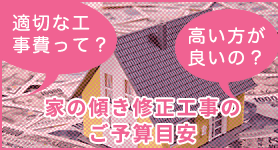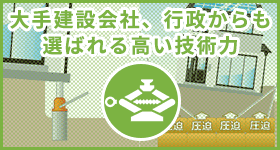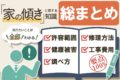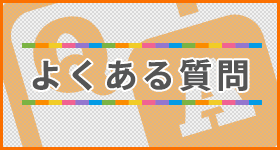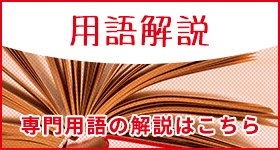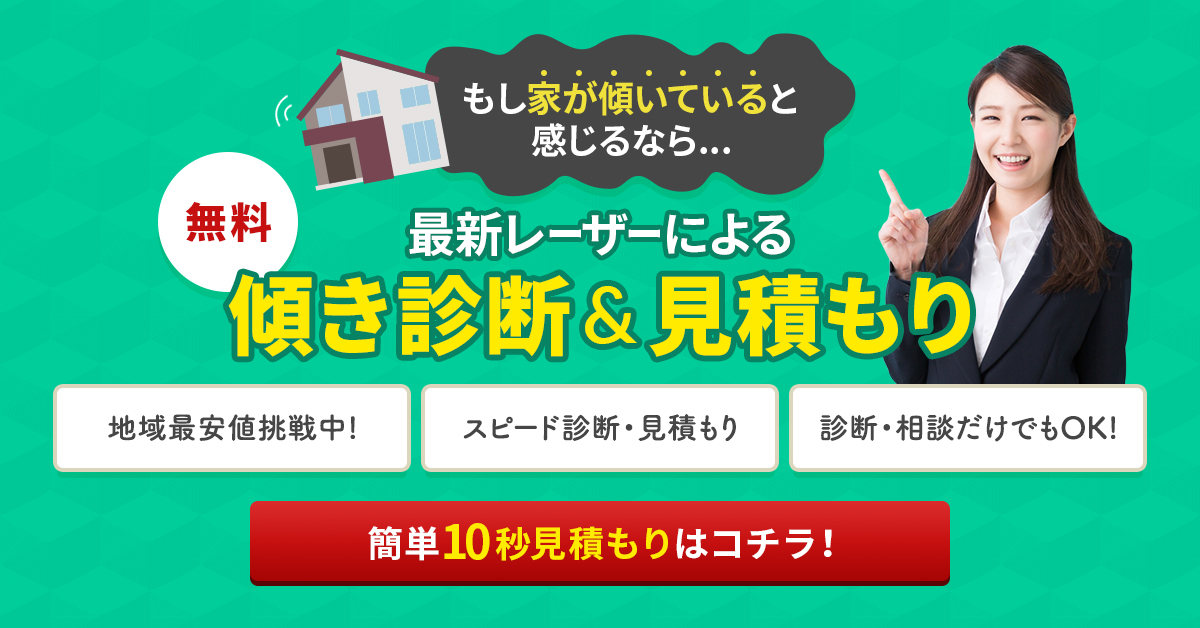礫(れき)とは
礫(れき)とは、岩石が細かく砕けてできた石のかけらのことです。大きさが2mm以上の粒子を礫と呼びます。砂よりも大きく、岩よりも小さい石のことで、川原や海岸、山の斜面などでよく見られます。
礫の種類と分類方法
礫は大きさによって分けることができます。一般的に次のように分類されます。
| 名前 | 大きさ | 特徴 |
|---|---|---|
| 細礫(さいれき) | 2mm~4mm | 砂利の中でも小さいもの |
| 中礫(ちゅうれき) | 4mm~20mm | 一般的な砂利の大きさ |
| 大礫(だいれき) | 20mm~75mm | 大きめの砂利 |
| 玉石(たまいし) | 75mm~300mm | 握りこぶし程度の大きさ |
| 巨礫(きょれき) | 300mm以上 | 大型の石 |
また、礫は形によっても分けられます。川で長い間水に流されてまるくなった「円礫」、角が残っている「角礫」などがあります。
礫の形成過程
礫は主に次の方法でできます。
- 風化作用:岩が風や雨、温度変化などで少しずつ砕けてできる
- 侵食作用:川の流れや波の力で岩が削られてできる
- 運搬作用:川や海の流れで運ばれていく間に、ぶつかりあって角が取れて丸くなる
礫の工学的特性
礫は土や砂と比べて、とても強い地盤になります。礫が多い地盤は水はけがよく、重い建物を支える力も強いです。ただし、礫と礫の間に空間があると、地震の時に崩れやすくなることもあります。
地質調査における礫の重要性
地面の下にどんな礫があるかを調べることは、建物を建てる前にとても大切です。礫の種類や大きさ、どのくらい固まっているかを知ることで、その場所が建物を支えられるかどうか分かります。また、礫がどこから来たのかを調べることで、昔その場所がどんな環境だったかも分かります。
建設・土木工事における礫の影響
建物や道路を作るとき、礫が多い地盤は良い面と悪い面があります。良い面は、地盤が強く水はけが良いことです。悪い面は、大きな礫があると掘るのが難しかったり、杭を打ち込めなかったりすることです。工事の前に地面の下の礫の様子をよく調べることが大切です。
地盤改良と礫質地盤の対策方法
礫が多すぎたり大きすぎたりすると、建物の基礎を作るのが難しくなります。そんな時は地盤改良という方法で、地面を使いやすくします。例えば、礫と礫の間に特殊なセメントを流し込んで固めたり、大きな礫を取り除いたりします。
礫地盤の調査方法
礫がある地盤を調べるには、主に以下の方法があります。穴を掘って直接見る「ボーリング調査」、地面を叩いて音や振動で調べる「物理探査」、重い錘(おもり)を落として地盤の強さを測る「標準貫入試験」などです。礫が多いと調査が難しくなることもあります。