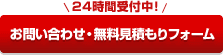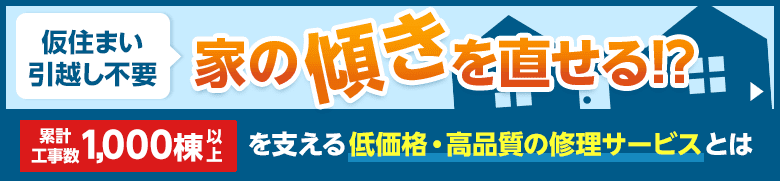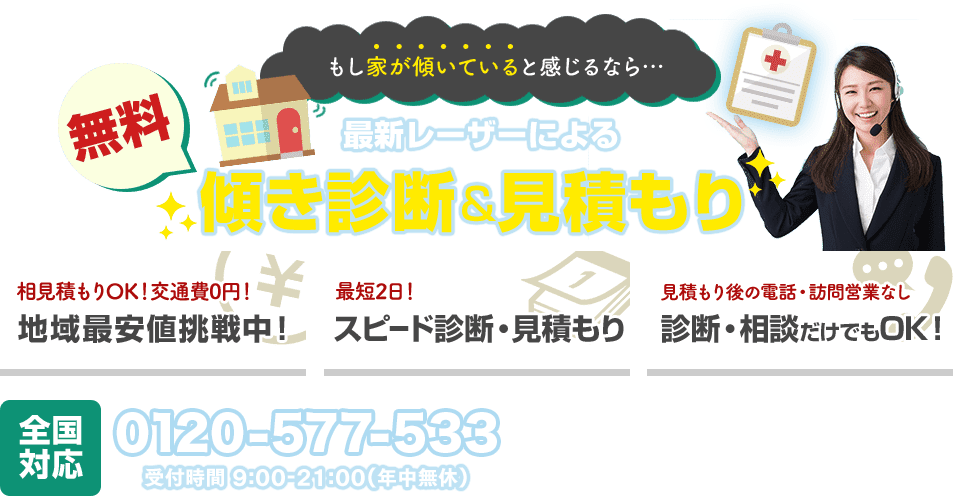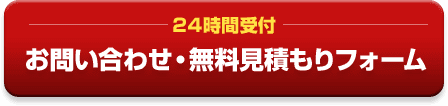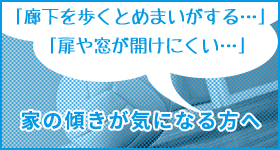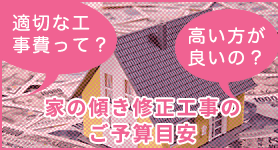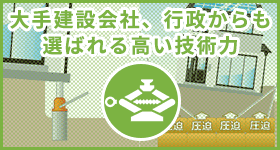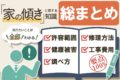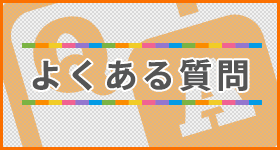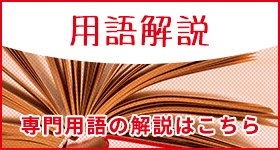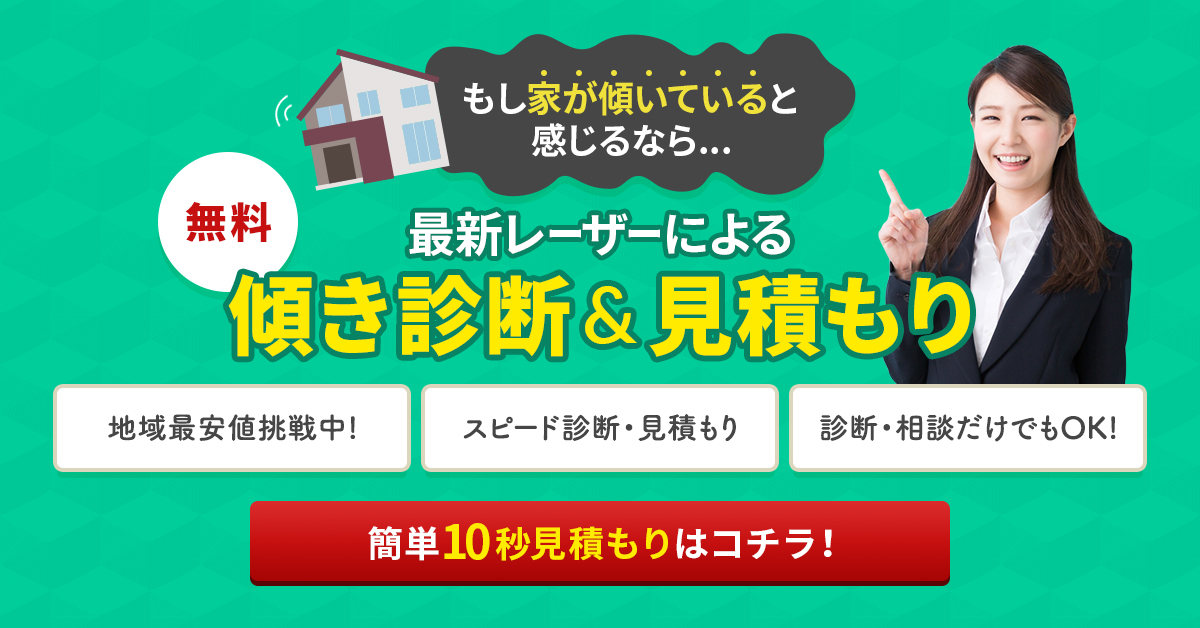砂利層とは
「砂利層」とは、小さな石や砂のように粒が大きいものがまとまって積もり、層になっている部分をいいます。土とは違って空(あ)きが多く、水が通りやすいのが大きな特徴です。地面の中を考えるときに、粘土のような細かな粒が多い層と区別してとらえるとわかりやすいでしょう。
砂利層の主な特徴
砂利層は粒が大きいため、土のように固くしまった状態になりにくい反面、水はけが良いという特性を持ちます。粒と粒の間にすきまが多いので、雨が降ったときなども水が地中へ浸透(しんとう)しやすいです。ただし、固め方によっては重い建物を支える力に不安が出る場合もあります。
地盤における砂利層の役割
建物の土台になる地盤を考えるとき、砂利層が下の方にあると排水性が良くなるため、水がたまりにくい地面がつくりやすくなります。一方で、地震が起きたときに砂利と水が混ざって流動化しやすいケースもあり、砂利層があることで液状化(えきじょうか)の心配が出ることもあります。
砂利層が形成される経緯
川の流れや海の波によって、小石や砂が運ばれ、それが長い時間をかけて積み重なっていくと砂利層になります。山から流れ出た石が川を通じて丸く削られ、その後、平野部などに堆積(たいせき)していくことで層ができあがるのです。
砂利層がもたらすメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 水の通りが良く、排水性に優れる | 液状化のおそれがあり、揺れに弱い場合がある |
| 地面が湿りにくく、カビや湿気を防ぎやすい | 粒が大きい分、固まりにくく施工に注意が必要 |
調査や確認方法
砂利層の存在や厚みを調べるには、地面を掘って土の状態を直接見る方法や、地中の硬さや水分量などを測定する調査が使われます。これらの結果をもとに、建物を支えるのに十分な強度があるかや、水がたまりにくいかなどを判断します。
施工時の注意点
- 水が抜けすぎないように、下地に粘土質の土を入れるなど工夫する
- 建物の重さに合った地盤改良を行い、必要に応じて補強材を活用する
- 大きめの砂利が多い場合は、しっかりと締め固める作業が重要
- 近くに地下水があるときは、過剰に水が流れ込まないよう排水計画に配慮する